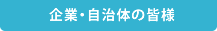レポート日記
一覧に戻る「シアターで話そう。 ~映画館からまちが変わるには~」

開催日:2011年11月26日
通常授業
映画は今も昔も変わらない娯楽として多くの人に愛されています。
しかも、福岡は人口あたりの映画館の割合が日本トップと、映画との距離が近いまちでもあります。
そんなまちで60年以上も昔から営業し続けている映画館で、まちと映画館のこれからについての授業を開催しました。

会場になった映画館は中洲に在る中洲大洋映画劇場さんです。
今回はそちらで映画の試写等を行なている、シアタールームをお貸し頂きました。

会場がシアターですから、授業は映画の視聴から始まりました。
上映した映画は、『小さな町の小さな映画館』という作品です。
北海道の人口わずか1万人程のまち、浦河で90年以上にも渡って人々に愛されていた映画館の話には、今回の授業のテーマを考えるヒントが沢山詰まっています。
この映画館には、まちが活気に溢れて映画館も大盛況だった時代もあれば、赤字に苦しんだ時代もありました。
それでも今まで大黒座が残っているのは、若者達が「浦河映画サークル」を立ち上げたり、まちの人々が参加する「大黒座まつり」が毎年開かれたり、「サポーターズクラブ」の支えが有るからです。
そして、そんな映画館からは、卵の生産者さんとそこの卵を買うパン屋さんとの交流や、週の半分を映画館の看板を製作する女性が生まれ、映画館はまちのコミュニティの核になっています。

そんな映画を鑑賞した後は、ここ福岡での映画館について、皆さんと考えてみました。
まずは中洲大洋の歴史についてです。
中洲大洋は大正2年に日本初の洋画契約を結んだ映画館として開業し、空襲の被害も乗り越えながら今も営業を続けています。その間、幾多の名画を上映し続け、最盛期には朝7時台から上映を始めてもお客さんの行列が耐えなかった事も有ったそうです。
そんな歴史有る素晴らしい映画館とのこれからの付き合いにはどんな形があるのでしょう?

「作り手の思いはスクリーンの大迫力で見てほしい」
続いてお話を伺った、レンタルショップを運営する会社で働く笠井さんからは、熱いお言葉を頂きました。
また、笠井さんの会社ではシネコンで絵本の読み聞かせをする事で小さい頃から映画館の空間に触れてもらう事業を行っているそうです。
そして、映画館側も、最近では企業の入社説明会や結婚式の二次会会場への貸し出しも行なわれているそうです。

さて、私達にはどんな思いがあるのでしょう?
最後のワークショップでは、
「そもそも、映画の魅力とは?」
「ローカルこそ出来る魅力は?」
「単発で終わらず、継続して色々な事に連動していくには?」
の3つについて、生徒の皆さんでお話頂きました。

会話はスタートから一気に盛り上がりました。

映画が好きで、好きな事について話す皆さんの顔は活き活きとしています。
発表頂いた内容はどれも具体的かつ、映画愛に溢れたものでした。
(一部紹介)
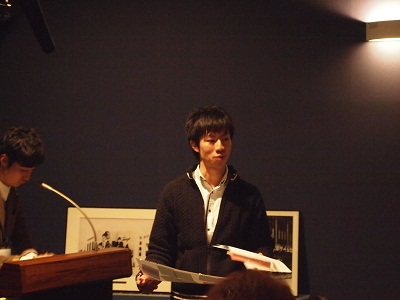

「非日常の映画の世界をみんなで観る良さ(花火と同じなのかも)」
「映画を観た後に感想を語り合える場が欲しい」
「一日映画館長制度をやってほしい」
「昔やってた、午前5時までの『山笠ナイト』は良かった」
「中洲にある映画館だから、のんびりお酒を飲みながら映画を観てみたい」
等々

実現して欲しいなぁ、あるといいなぁ、という意見がとても目立つ発表になりました。


いつかはテン大映画サークルなんかで実現してみたいですよね。
(おまけ)

授業の後も話の熱はなかなか冷めず。
映画を見た後の、あの「誰かと話したい」という気持ちが溢れた放課後なのでした。
(ボランティアスタッフ 山路 祐一郎)
【今回の先生】
【今回の教室】
住所 : 福岡市博多区中洲4-6-18