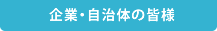レポート日記
一覧に戻る和の心で迎える正月 ~新年の振る舞いについて~

開催日:2011年12月23日
通常授業
師走の寒空の下、天神の中心にある水鏡天満宮で
お正月を目前に控えたこの時期にぴったりの授業が行われました。
この日は、福岡の文化や歴史を大切にする会「敬水会」や、
NPO法人「博多の歴史と文化の寺社町ネット」などで幅広くご活躍され、
テンジン大学でも5月に講師をしていただいた志村 宗恭先生を講師にお招きしました。
神社の中ということもあり、床の間のある畳の部屋では自然と背筋が伸びてきます。

まずは、基本的な畳のお部屋での振る舞いについて教えて頂きます。
和室でのご挨拶は、正座をして両手をついてお辞儀をします。
特に茶道や着物を着た時には、扇子を自分の前に置き、両手をつき丁寧にお辞儀をします。この自分の前に置いた扇子には、周りと境界をひく意味が込められているそうです。
謙虚に生きること、けれども誇りを持つこと、日本人が大切にしていた心の表れです。

よそのお宅にお邪魔したときには、まず初めに床の間拝見をします。
授業では、実際に床の間拝見を行い、作法を教えて頂きました。
座布団の降り方や座り方など、みなさん最初は戸惑っていらっしゃいましたが、
だんだんと所作が板についてきたご様子でした。
床の間というのは、神様や偉人を迎え入れるための場所でした。
現在では、偉人の代わりに掛け軸が掛けられ、
その家の大切なもの、季節のお花が飾られます。
この床の間は、いわばその家で一番大切な場所ですので、
初めに拝見させて頂きます。
現在では、床の間がないお家も多くありますが、
その場合はそのお家で一番大切にしている絵や写真などを見せていただくと、
喜ばれるそうです。

さて、授業は本題に入りお正月の迎え方についてのお話に移ります。
普段何気なく準備していたお正月用品一つ一つに、意味があります。
その一例をご紹介したいと思います。
・しめ縄・・・結界の意味。悪いものが家に入らないようにする。
・門松・・・古来より日本では松は神聖なものとされてきた。
神様の象徴を玄関に立てることで神さまを迎え入れる。
・お節・・・神様に供える(節供)ための料理。お供えしたあとにいただく。
・雑煮・・・神様にお供えするお節を作った残りの野菜で作るもの。
・お屠蘇・・・7~9種の薬草と酒で体を温め、寒い時期を乗り越える。
健康を願うもの、縁起物、全てに意味があるんですね。
ここで、お正月だけではなく
日常生活でも役立つお箸の使い方を教えていただきました。
右手でとり左手に持ち替え、右手で受け取るという作法には、
お箸を大切に扱う心が表れています。

今年の漢字は「絆」でした。
すべての絆は、家族の絆から始まるものだと先生はおっしゃいます。
お正月の準備を行い、家族でお正月を迎えることでその絆を改めて感じる
いい機会になるのではないでしょうか。
盛りだくさんの授業で全てご紹介できなくてとても残念なのですが、
私が一番印象に残ったお話をひとつだけご紹介して、
レポートを終わらせていただきたいと思います。
畳のお部屋での歩き方を今まで意識したことがありますか?
畳のお部屋では、畳をこする音を立て、薄紙一枚を引くように歩くそうです。
その昔、日本には忍者がいました。忍者は抜き足、
忍び足で移動することから、音を立てることが、
正々堂々と振る舞う証だとされたそうです。
また、和室では周りの人が座っていることからも
埃を立てないようにとの配慮からとも言えるそうです。
このように、些細なことでも思いやりを忘れない日本人の心意気を、
見直さなければならないことがたくさんありそうです。
授業が終わった頃には、
生徒の皆さんの歩き方や姿勢がすっかり変わられており、
先生に手をついて挨拶して帰るという光景が見られました。
板についた所作は素敵でしたよ。お疲れ様でした。

(ボランティアスタッフ 山内 結衣)
【今回の先生】
志村 宗恭(裏千家茶道教室教授/博多の文化と歴史「敬水会」主宰)
【今回の教室】
住所 :福岡市中央区天神1-15-14