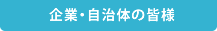レポート日記
一覧に戻るWATER PLANET – 「水」と向き合う一日

開催日:2012年03月11日
通常授業
今回は井尻駅近くの商店街内にある、イジリアートカフェでの授業です。

強い風(春一番?)が吹く中、暗くセッティングされた店内で授業が始まります。
今回は、イジリアートカフェで行われていた水と照明を使った作品展「WATER PLANET — 「水」と向きあう一日」の展示の中の1つとして福岡テンジン大学の授業を開催させて頂きました。

今回の展示作品を作られた照明デザイナーの馬渡先生にお話を伺います。
「これからのアカリを考える」ということをテーマに馬渡先生が考えられているアカリの3ポイントを軸にお話をして頂きました。
1.明るさへの価値観を見直す
昨年の3.11以降、節電が呼びかけられているが、灯りそのもののあり方を考えるべきだと先生はおっしゃいました。
東京各地や福岡でも各所で節電は実施され、コンビニなどのサイン照明なども消され、「見え辛くて怖い」という声もあれば「過度に照明を使いすぎず、これでもよいのでは。」など様々な意見が出たそうです。

2.光の色温度をデザインする
先生の紹介する写真を見て行き説明を受けるなかで、電灯には白っぽいものと、あたたかみを感じるものがあるのがわかっていきます。光には色温度があり、地球上のあらゆる光に存在しているそうです。それはサーカディアンリズムといって、人体や生活リズムにも影響しているとのこと。
3.Day Lightをデザインする
例えば海外のミラノなどの建築は積極的に自然光を取り入れる造りになっており、夕方はブルーのライトを灯したりと、雰囲気が良いそうです。
以前先生が仕事で手掛けられたイムズのカフェや大濠公園にある建物のエントランスも、心地よさを重視した暗さにされているとのこと。
日本に白熱灯が伝わって120年ほどが経ったらしく、「明るければ明るいほどよい」という考え方から、「心地よい明るさ」への変換が必要だと、先生はおっしゃっていました。
次はワークショップに移ります。
小さな電球のついたコードを床にはわせ、電球の上に紙やアルミなどを被せて、
皆さんでそれぞれの灯りの形を作っていきます。

暗い室内でカサカサと音がする中、生徒さん達(全員大人)が黙々と作業されている様子は少し不思議な雰囲気に感じましたが、真剣な表情が印象的でした。
はじめはカラフルな紙で、くしゃくしゃにしたり、くるっと丸めたり、思い思いに自由に作業して頂きました。他にも白い紙に統一してみたり、アルミ素材で統一してみたり、様々なパターンを試されていました。

ここで「改めまして」の自己紹介をしていきます。
途中一人の生徒さんからの提案で、昨年の震災の話になり、ちょうど当時の時間にさしかかっており、その場の全員も1分間程の黙祷を捧げました。
自己紹介の後は皆さんで作った灯りの間に人形を置いて行き、全体を「街」に見立てていきました。足元に、今日だけの独特な夜景がったように感じました。

全体的に「灯り」について考える内容になりましたが、
水の息づかいが感じられる照明空間での授業は、
今日の事をより印象深くしてくれたのではないかと思います。
ご参加頂いた皆さん、お疲れさまでした。

(ボランティアスタッフ 立石 依里)
【今回の先生】
【今回の教室】
住所 : 福岡市南区井尻4丁目3-16