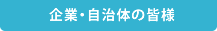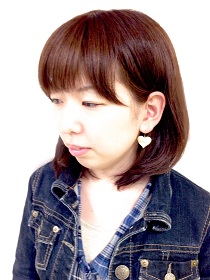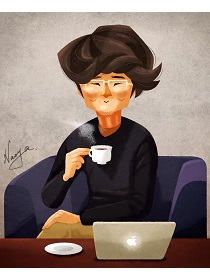レポート日記
一覧に戻る[テン大授業づくりシリーズ] ~チームを動かすサイクルとエンジン編~

開催日:2014年03月22日
通常授業
今回の授業はテン大授業づくりシリーズ第3弾。
第1弾では相手を口説くタイトル&告知文について、また、第2弾では想いをカタチにする企画編、そして今回がシリーズ最終回、チームを動かすサイクルとエンジン編です。
テンジン大学の授業企画のマネジメントを例にチームの企画・運営面の継続的な運営について学んでいきます。
まずは、グループ内で自己紹介を兼ねて、今、自分の所属するチームや組織での悩みを話し合います。
今回の授業は前半がサイクルとエンジンについての理論、後半はゲームを交えた理論の実践という形式です。
サイクルについて
テンジン大学の授業は授業コーディネーターと呼ばれるスタッフによって、好きなことを授業にするというスタンスのもと、企画・実施されています。
授業コーディネーターたちの年齢も職業も価値観もバラバラ。
では、テンジン大学の授業はどのようなサイクルで成り立っているのでしょうか。
テンジン大学の授業の作り方は
授業企画→事前準備・当日運営→振り返り(フィードバック)→改善
という流れで行われます。これは、PDCAサイクルに沿ったもの。
PDCAサイクルとは?
Plan(計画)→Do(実施・計画)→Check(点検・評価)→Act(処置・改善)
テンジン大学ではこの一連のサイクルを繰り返すことで、授業の質を上げています。
さらに、授業の質を一定に保つために、企画シートをフォーマット化して、5W1Hでタイムスケジュール、タイトル、告知文を書き込むことで、個人の能力によらず、誰でも授業がつくれるような仕組みづくりをしています。
企画というと、センスや能力がある人だけができるものと思いがちですが、テンジン大学には誰でも自分の想いをカタチにできる仕組みがあるからこそ、毎月、授業を続けることができるんですね。
エンジンについて
エンジンとはチーム・組織のモチベーションのことです。
ダニエル・ピンクによるとモチベーションには3段階あります。
(モチベーション3.0 ダニエル・ピンク著)
モチベーション1.0
衣食住を満たすための生物として生きるための基本的欲求に対する動機付け
モチベーション2.0
ボーナスまたは罰金、昇進、表彰、他者からの賞賛や承認、メンバーからの受容、リーダー・上司の配慮による外発的動機付け
モチベーション3.0
社会への貢献、人間的成長、知的興奮などより高い次元での意味づけを持つことによる動機付け
モチベーション2.0は20世紀のルーチンワークには有効でしたが、創造性が必要とされる仕事が増えてきている現代においては合わず、仕事の質や成果が上がらなくなってきています。
つまり、これやっといてでは、人は動かせないのです。
テンジン大学でも、スタッフがやりたい、社会に発信したいことをもとに、テンジン大学でできることと社会のニーズとの接点を探りながら、授業の質を上げています。
谷口さんが授業の質を上げる為に大切にしていること
*とにかく、相手の言葉に耳を傾ける。
*指示をするのではなく、対話の中で気付きを与えるような質問をする。
*たまには呑みニケーションも!!
何よりも信頼関係を大切にすることで、相手の行動が変わり、それがチームや組織にとって良い結果を生むのだそうです。
ここまでが理論
後半は前半に学んだPDCAサイクルの実践です。
その前にみんなで性格診断をしました。
20個の質問に回答し、4つのタイプに分類
人や物事を支配していくコントローラー
分析や戦略を立てていくアナライザー
人や物事を促進していくプロモーター
全体を支持していくサポーター
4つの性格タイプがばらけるように席替えをし、自己紹介の後はいよいよゲームの時間です。
チーム対抗ゲームの内容は折り紙で大きな輪っかをつくるというシンプルなもの。
まず、1人リーダーを決めます。
リーダーは指示のみ可能で最終決定権があります。
計画10分、制作20分、途中でやり方を変えてもOK!
そのあとは、フィードバック(反省をもとに改善策を見出す)をします。
DJ山路さんの軽快な音楽とともに、ゲームがスタート。
ひたすら折り紙を切り、つなげていく…。
静かで熱い戦いです。
チームによって作戦は様々で、細く長く、見た目は気にしないところや、太めに折り紙を切りつなげ、最後に真ん中を切りメビウスの輪のようにしたチームも。
20分後。
教室からはみでるくらいに長い、輪っかができました。
輪っかの完成後はフィードバックの時間です。
次に向けての反省と改善策をチームで話し合います。
折り紙を繋げる為のテープを切るのに苦戦した、1人が見つけた効率がいい方法をもっと早く共有できたらなどの意見が出ていました。
今回のゲームはすごく簡単なものでしたが、PDCAサイクルの良い練習になったのではないでしょうか。
とにかくやらなければ、成果も上がらないし、改善策も出てこない。
行動するって、改めて大切だなと実感しました。
今回のまとめ
*様々な流れをサイクル化することで、持続のしくみをつくる。
*人は信頼の上に成り立っている。
*信頼を築くことがチーム・組織の成果や成長につながる。
すぐに効果がでなくても改善しながら続けること。楽しみながら♪
おわりに
今回の授業づくりシリーズを企画したのはなんと大学4年生の齊藤麻子ちゃんです。
彼女はこの春大学を卒業する為、テンジン大学は一旦卒業して、今後は個人サポーターとしてテンジン大学を支えてくれます。
彼女がこの授業を企画した理由はテンジン大学開校以来3年間、授業を企画面から支えてきた広告企画・制作のプロである、谷口さんの持つノウハウを学生のみなさんに還元したい、また、この授業を通して「街のプロデューサー」をもっと増やしたいというもの。
これからもテンジン大学では街に愛着を持つ人を増やし、そこからアクションを起こして街のプロデューサーが生まれるような授業を企画していきますので、お楽しみに!
(ボランティアスタッフ 瀬崎 麻美)
【今回の授業コーディネーター】
【今回の先生】
【今回の教室】
住所 : 福岡市中央区天神3-15-1 にちりんビル3F